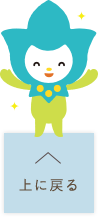作業環境測定

有害な業務を行う屋内作業場は、環境の状態によって業務上疾病にかかる恐れがあります。企業にとって、作業環境を把握し、労働者に安全な環境を提供することは、最低限行わなければならない義務です。
よぼういがく協会では、作業環境測定機関として、各種作業環境測定を行っています。
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類など
| 作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
測定の種類 | 測定回数 | |
|---|---|---|---|
| 1土木・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の濃度及び粉じんの遊離けい酸含有率 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 2暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業場 | 気温・湿度及ふく射熱 | 半月以内毎に1回 | |
| 3著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 4坑内の作業場 | イ.炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガスの濃度 | 1ケ月以内毎に1回 |
| ロ.28℃を超える作業場 | 気温 | 半月以内毎に1回 | |
| ハ.通気設備のある作業場 | 通気量 | 半月以内毎に1回 | |
| 5中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2ケ月以内毎に1回 | |
| 6放射線業務を行う作業場 |
イ.放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量当量率 | 1ケ月以内毎に1回 |
| ロ.放射性物質取扱作業室 | 空気中の放射性物質の濃度 | ||
| ハ.坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | |||
| 二.坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場 | |||
| 7 | 特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 空気中の第1類物質または第2類物質の濃度 | 6ケ月以内毎に1回 |
| 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 空気中における石綿の濃度 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 8一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内毎に1回 | |
| 9酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 空気中の酸素濃度 | その日の作業開始前に | |
| 硫化水素発生危険場所は、空気中の酸素及び硫化水素濃度 | |||
| 10有機溶剤(第1種または第2種)を製造し、または取扱う屋内作業場 | 空気中の有機溶剤の濃度 | 6ケ月以内毎に1回 | |
※1、6-ロハ、7、8、10は、作業環境測定士に行わせるか、作業環境測定機関に委託して行わなければなりません。
※6放射線業務を行う作業場について、当協会では測定を実施しておりません。
個人ばく露濃度測定
作業環境測定とは別に、作業者個人にサンプラーを装着し、作業者がばく露する有害物質を把握する測定があります。作業管理等の見直し、リスクアセスメントのための情報として有用であり、作業環境測定を補完するものです。作業環境測定と併せての実施をお勧めしています。
作業環境測定機関としての登録
作業環境測定機関 岩手労働局 登録番号 3-2 登録日 1978(昭和53)年7月20日

室内空気環境測定

住宅や学校等の新築,リフォーム後、目がチカチカする、めまい、頭痛や吐き気がするなどの症状が出る場合があります。その原因として、建材・家具などから発散する揮発性有機化合物(VOC)が影響している可能性が考えられます。
よぼういがく協会では、居住空間での健康障害防止のため、住宅から施設や学校までの揮発性有機化合物の測定を行っています。
- 測定対象物質
- ホルムアルデヒド/トルエン/キシレン/パラジクロロベンゼン/エチルベンゼン/スチレンなど

ダニアレルゲン検査
アレルギー性の病気をかかえた子どもたちが増えています。アレルギーの原因物質は様々ですが、ダニ又はダニアレルゲン検査は快適な居住環境を維持するために重要視されています。文部科学省は、年1回の定期的なダニ又はダニアレルゲン測定の実施を「学校環境衛生の基準」で定めています。
よぼういがく協会では、この基準に基づいたダニアレルゲン検査を行っています。

レジオネラ属菌検査
レジオネラ属菌に汚染された入浴施設などで飛散したエアロゾルを吸入すると、レジオネラ肺炎やポンティアック熱を発症することがあります。特に新生児,高齢者や免疫機能が低下している人は発症のリスクが高いとされています。公衆浴場や旅館などでは、レジオネラ属菌検査が法律により義務づけられています。
よぼういがく協会では、循環式の入浴施設、ビルの冷却塔などの水質検査を行っています。